皆さんこんにちは。
静岡県沼津市を拠点に介護DXを活用し、医療・介護の現場を支えるために、ナースコール設置やAI見守りカメラのワンストップサービスを提供しております株式会社N-TEC(エヌテック)です。
「ナースコールを押してほしいのに、利用者が押してくれない」「転倒や急変に気づけなかったらどうしよう」と、不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。実際に、認知症や身体機能の低下、さらには「申し訳ない」という心理的な理由から、ナースコールを押さないケースは少なくありません。
この記事では、ナースコールを押せない原因から、従来行われてきた工夫、そして介護DXを活用した最新の対策までを分かりやすく解説します。介護施設や病院で利用者の安全とスタッフの業務効率を両立させたい方は、ぜひ参考にしてください。
■ナースコールを押せない原因

ナースコールは、患者や利用者が体調の変化やトイレ介助などの「助けが必要なとき」にスタッフへ知らせる大切な手段です。しかし、現場では「押せない」「押さない」といった状況が少なくありません。その原因を理解することは、転倒や急変を予防し、安心できるケア環境を整える第一歩です。ここでは代表的な理由を3つに分けて解説します。
・身体的に押せない場合
加齢や病気の影響で筋力が低下し、ナースコールのボタンを押す力が足りないケースがあります。また、関節の動きが制限されている場合や、ベッド上の体勢によって腕を伸ばせないといった身体的な要因もあります。施設や病院では「設置位置を調整する」「大きめのボタンにする」など、身体状況に合わせた工夫が必要です。
・認知症で押さない場合
認知症の方は「どのボタンを押せばよいか分からない」「押すタイミングを忘れる」といった記憶や判断力の低下が原因になることがあります。ナースコール自体を理解できない場合もあり、その結果としてトイレで困っても知らせられないことがあります。スタッフが巡回時に観察を強める、分かりやすい色や形の機器を導入するといった対応が求められます。
・トイレなどで遠慮する場合
心理的な理由で「ナースに迷惑をかけたくない」「申し訳ない」と感じ、押さない利用者もいます。特にトイレ介助など日常的な行動では、「自分でできる」と無理をして転倒につながるケースも少なくありません。看護師や介護スタッフが声かけや説明を行い、安心して呼出できる環境をつくることが重要です。
■押さないことで起きるリスク

ナースコールが押されないまま時間が経過すると、利用者にとっても介護・看護スタッフにとっても大きなリスクが発生します。特に高齢者や認知症の方では、状況の変化を自分で伝えられないことが多いため、注意が必要です。ここでは代表的なリスクを解説します。
・転倒や急変の見落とし
トイレやベッドからの移動で無理をした結果、転倒して骨折につながることがあります。また、呼吸困難や胸の痛みなど急変があってもナースコールで知らせられなければ、早期対応が遅れてしまいます。スタッフの巡回やセンサーによる察知を組み合わせることで、押せない場合でも異常を早く発見する工夫が必要です。
・介護者側の負担増加
ナースコールが押されずに事故が起きると、緊急対応や追加のケアが必要となり、施設や病院の業務負担が増します。また、スタッフが「なぜ知らせてくれなかったのか」と感じることで心理的ストレスにもつながります。押さない理由を理解し、利用者が安心して呼出できる環境を整えることが、スタッフの業務を守るためにも重要です。
■従来の対策と工夫

ナースコールを押さない・押せない問題は、昔から介護や病院の現場で課題とされてきました。そのため、従来から行われてきた基本的な対策や工夫がいくつもあります。こうした方法は、利用者の状況に応じて今も有効であり、介護DXを導入する前の土台として欠かせません。
・ナースコール指導やパンフレット
施設や病院では、新しく入所・入院した利用者に対してナースコールの使い方を説明します。具体的に「どのボタンを押せばよいか」「どんなタイミングで呼出すのか」を伝えることで安心感につながります。文字や図を使ったパンフレットを用意することで、認知症のある方や耳が遠い方でも理解しやすくなります。
・ボタンの位置や形の工夫
ベッドに固定されたタイプのボタンは、利用者が寝返りを打った際に届かない場合があります。そのため「手元に置ける端末型」や「押す力が弱くても反応する大きめのボタン」などを検討することが有効です。利用者の身体的な状況に合わせて設置環境を見直すことが転倒予防にもつながります。
・心理的負担を減らす支援
「トイレで呼ぶのは申し訳ない」と感じる利用者には、スタッフから「遠慮せず呼んでください」と繰り返し伝えることが効果的です。定期的な巡回や声かけで、呼出をためらわない関係性を築くことも重要です。心理的なハードルを下げることで、ナースコールを安心して活用できる環境が整います。
ナースコール鳴りっぱなしを解決!現場でできる3つの対応策
■介護DXによる新しい対策
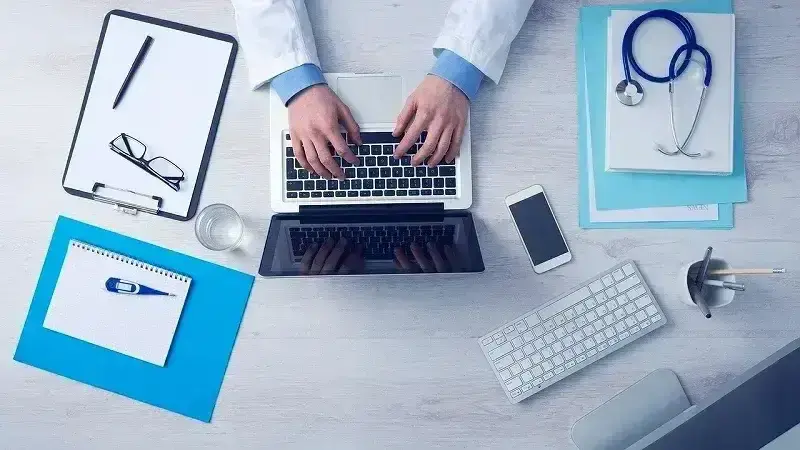
近年は、従来の工夫に加えて介護DX(デジタル技術を活用した介護の効率化)が進み、ナースコールを押せない場合の補助手段として導入が広がっています。センサーやシステムを組み合わせることで、利用者がボタンを押さなくても異常を察知できる環境が整いつつあります。
・センサーで転倒や離床を検知
ベッドや床に設置するセンサーは、利用者が立ち上がったタイミングや転倒した状況を自動で通知します。これにより、押せないまま倒れてしまうリスクを減らせます。身体的にボタン操作が難しい方にとって有効な方法です。
・見守りシステムで安心を提供
映像や行動データを活用する見守りシステムは、病室や居室の状況をスタッフが遠隔で確認できる仕組みです。患者や利用者が呼出しをしなくても、スタッフが異変を察知して素早く対応できるため、安心感が高まります。
・頻回コールへのデータ活用
ナースコールを頻回に押す方に対しては、その回数やタイミングをデータ化して分析することが可能です。「夜間に集中している」「トイレ利用時が多い」など行動パターンを把握することで、予防的なケアや業務の効率化につながります。データに基づく対応は、スタッフの負担を減らすだけでなく、利用者の満足度向上にもつながります。
介護DXを導入したお客様事例
■まとめ

ナースコールを押さない・押せない状況には、身体的な要因、認知症による判断力の低下、遠慮や「申し訳ない」という心理など、さまざまな理由があります。そのままにしておくと、転倒や急変の見落としといった重大なリスクを招き、利用者だけでなくスタッフの業務負担にも直結します。
従来の取り組みとしては、ナースコールの使い方を丁寧に説明する指導やパンフレットの活用、ボタンの設置環境や形状の工夫、スタッフからの声かけによる心理的サポートなどが有効です。これらは今も現場で必要不可欠な対策です。
さらに近年は、介護DXの進展により、センサーや見守りシステムを活用した補助が可能になっています。押さなくても異常を察知する仕組みや、ナースコールの利用回数をデータで把握する方法は、事故予防と業務効率化の両方に役立ちます。
今後は、従来のケアとデジタル技術を組み合わせることで、利用者が安心して生活できる環境を整え、スタッフが負担を減らしながら質の高いケアを提供することが期待されます。
■介護現場の「困った」をN-TECにご相談ください!

N‑TECは静岡県沼津市を拠点に、ナースコールや見守りカメラの設置、介護記録の電子化など、医療・介護現場に特化したDXソリューションを提供しています。
施設ごとの現場状況やニーズを丁寧にヒアリングし、最適な通信設備やデジタル機器を組み合わせて導入。設置だけでなく、保守・メンテナンスまで一貫してサポートするため、現場スタッフは安心して本来の業務に集中できます。経験豊富なスタッフによる現場調査と提案で、実際の課題に即した具体的な改善策を提示可能です。
「夜間の巡回や見回りの負担を減らしたい」「介護記録作業の時間を短縮したい」「スタッフ間の連携をスムーズにしたい」「通信環境のトラブルを未然に防ぎたい」といったお悩みも、N‑TECなら現場調査から改善プランの作成、機器導入、運用サポートまでワンストップで対応。AI見守りカメラやスマートナースコールなど最新機器を活用して安全性と効率を両立させ、導入効果やコスト削減も明確に提示します。
小さなことでも、まずはお気軽にご相談ください。施設ごとの状況に合わせ、現場を確認したうえで最適なソリューションをスピーディーかつ丁寧にご提案いたします。あなたの医療・介護現場の課題を一緒に解決し、安全で働きやすい環境を実現しませんか?
▼関連記事▼
生産性向上推進体制加算とは?介護施設での導入をわかりやすく解説 !


